

発達障害の子の勉強で悩まれている方「子どもが勉強してる時、あまりに進みが悪くてイライラしちゃう。子どももイラついてる。今より上手くいく勉強方法が知りたい」
お子さんの勉強を見ていると、親御さんがイライラしてしまう…そしてお子さんもイライラ…。
勉強が親子にとって、ストレスが溜まりやすい時間になること、ありますよね。
特に、お子さんが発達障害の場合、配慮しなければいけない点が、多々あります。
そんな発達障害のお子さん・親御さんのイライラを、少しでも減らしつつ、「今より上手くいく勉強方法」をまとめてみました。
この記事を執筆してる私は、お子さんの療育/学習支援を15年以上しており、現在も支援に携わってます。
その経験を元に、3つの原因に分けて、実際に上手くいった方法を、短期/長期的な視点でお伝えします。
参考になれば幸いです。
目次
発達障害の子が勉強で「イライラする原因」

発達障害の子が勉強で「イライラする原因」は、3つあります。
①:勉強を「やりたくない」
②:勉強に「集中できない」
③:勉強が「分からない」
勉強をやりたくない
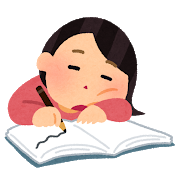
お子さんが勉強を「やりたくない」と感じる理由は、
勉強することで得られる、楽しみ(メリット)が少ない場合になります。
問題が解けて、達成感を感じたり、ほめてもらって喜びを感じる機会が少なかったり、
「間違い」に対する指摘が続くと…勉強のモチベーションが下がることに繋がります。
例えば、ダイエットする多くの人のモチベーションは…
・痩せてきれいになりたい
・ワンサイズ小さい服を着たい
・誰かを見返したい
など、自分が実感できる喜び(メリット)の為にしています。
このように、人が何かを頑張る時は、自分の満足(達成感)や周りに認めてもらえる(承認)ことが、大切になります。
特に、発達障害のお子さんは、やることの意義を見出しづらかったり、拒否感が強いことが少なくありません。
勉強をすることで得られる、喜び(メリット)が、勉強をする土台になります。
勉強に集中できない
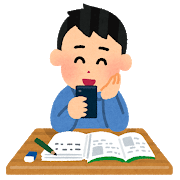
発達障害の子が、勉強に集中できない大きな原因は、
「注意特性(注意の切り替え・集中の持続など)」にあります。
例えば…
・音に敏感で注意が散りやすい
・気になる物が視界に入ると、衝動的に触る
・機嫌、空腹、眠気等で集中力に波がある
このように、集中力を散らす元(物や音)が近くにある環境だと、集中しにくくなります。
発達障害の子は、
・注意散漫
・感覚の過敏さ
・多動、衝動性が高い
などの、特性をもつことが多い為、勉強しやすい環境作りも、大切になります。
勉強が分からない
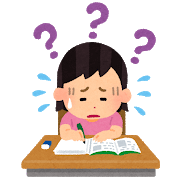
勉強方法が、お子さんの特性とミスマッチしている場合になります。
例えば、音を聞いた方が覚えられる子(聴覚優位)に、ひたすら書いて漢字を覚える勉強方法をする等です。
発達障害の子は、得意・不得意がハッキリしていることが多いです。
そのため、お子さんの得意な学び方を把握して、その学び方に合わせた、勉強をする必要があります。
発達障害の子の「短期的な勉強イライラ対策」

今より、勉強がスムーズになる「短期的な対処法」を4つ、見ていきます。
原因別に、1つずつお伝えします。
①:「今日のゴール」を視覚化する
(原因:勉強やりたくない)
②:勉強の後の「楽しみ」を決めておく
(原因:勉強やりたくない)
③:勉強を「妨げる要素」をなくす
(原因:勉強に集中できない)
④:本人の「得意な学び方」に合わせる
(原因:勉強が分からない)
今日のゴールを視覚化する

『その日の目標を視覚化』して、リビングなど、見える所に貼る方法になります。
これがあると、下記の効果が期待できます。
・見通しが立つ(頑張りやすい)
・進んでる実感が持てる(やる気UP)
「見通しが立つ」は、ゴールが分かるので、頑張りやすいです。
例えば…マラソンをする場面で、下記の様に言われたら、どちらの方が頑張れるでしょうか…?
「今から走って下さい」
「100メートル先のコンビニまで、走って下さい」
ほとんどの方は、後者の方が頑張りやすいと思います。
理由は、「ゴールが明確」だからです。
このように、ちょっとしたことでも、ゴールを視覚化(いつでも確認できる状態)することで、
お子さんの “頑張りやすさ” は変わってきます。
ちなみに、ゴール(目標)を書くのは、
紙に「国語の宿題プリント3枚」や「○問解く」など、具体的であれば大丈夫です。
お子さん・家族が、共通認識を持てていれば、問題ありません。
勉強の後の楽しみを決めておく

勉強を始める前に、「勉強終わったら、○○していいよ」など、
事前に楽しみを伝えておくことが、大切になります。
楽しみは、お子さんの好きなことになるので、お子さん自身に決めてもらいましょう。
✅「細かくほめる」も効果的
「宿題全部終わったらほめる」より、
「3問解けたらほめる」
「プリント1枚終わったらほめる」など、お子さんに合わせて細かくほめると、頑張りやすいです。
ちなみに、私が今まで支援してきた子の例ですと…
・家族がほめてくれる
・花丸、シールがもらえる
・点数をつけてもらえる
(前回より点数UPだとやる気UP!)
などが、多かったです。
勉強を妨げる要素をなくす
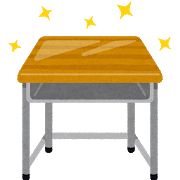
「集中力が散る原因」を、取り除くことになります。
意外と、これをしていない方が多いです…。
こちらが参考例になります。
・休憩を細かくとる
・気になる物は視界に入らない様に片付ける
・勉強の時間、兄弟姉妹にも静かに過ごすのを協力してもらう
などになります。
「お子さんが気になってしまう物」は、勉強をする時間にお子さんが「よく触っているもの・していること」になります。
普段の生活の様子から、見つけられると良いです。
また、集中力は、療育の現場では、「注意特性」と言われます。
勉強に特に影響が出やすい②つのタイプをまとめました。
該当する項目があれば、参考にご覧くださいませ。
【注意の切り替えが激しい】※注意の転動性
・ゴールを視覚化して伝える
・気になる物を片付けておく
・やるべき物だけ目の前におく
・気になる音が響かない場所を選ぶ
・終わった後にできることを伝えておく
・イヤーマフを使う
【注意を向け続ける 苦手】※注意の持続性
・細かくほめる
・課題を細かく区切る
・休憩を細かく入れる
イヤーマフとは、遮音性の高いヘッドホンになります。
聴覚過敏の子や、音を気にせず集中したい子が使いやすい物になります。
この記事の後半に、私が支援している子が使ってる、イヤーマフを載せておきます。
ご存知ない方は、参考程度にご覧ください。
本人の得意な学び方に合わせる

お子さんの『得意な学び方』に合わせて、勉強をすることが、大切になります。
お子さんが、どのタイプに当てはまるか、見てみましょう。
✅目で見て覚えるが得意 ※視覚優位
・図解やイラストを使う
・覚えたことを自分で、図を書いて整理
・解き方を、目の前で実際に見せてもらう
✅耳で聞いて覚えるが得意 ※聴覚優位
・動画の音声を活用する
・歌/語呂合わせで覚える
・視覚的な情報は最小限にする
(聴覚情報に意識を向けやすくする為)
✅全体像を掴んで理解が得意 ※同時処理
・マインドマップを使う
・全体像を図でまとめる
・お手本を見ながら学ぶ
・結論だけ把握し、後は自分で考えてもらう
✅手順通りに進めるのが得意 ※継次処理
・手順表を使う
・工程を1つずつこなす
・1つ覚えて、次の1つと進めていく
✅読みが苦手
・音声入力を活用する
・タイピングを覚える
・教科書を拡大コピーする
・文節ごとに斜線を入れる
・”読む行” 以外は紙や定規で隠す
✅書きが苦手
・漢字は意味に結びつけて覚える
・板書の代わりにタブレットで撮影する
・タイピングを覚える
・音声入力を活用する
✅計算が苦手
・ブロックなど物を実際に使って計算する
・アプリを利用して計算を楽しむ
・1文ずつ絵にしながら最後に計算する
・マス目のあるノートを使う
(絵の計算がしやすくなる)
もし、どのタイプが分からない…という方は、実際に試してみて、比べてみましょう。
お子さんに進めやすかった方法を聞くのが、一番早く確実な方法になります。
✅どうしてもイライラする時は「その場を離れる」
『タイムアウト』と言われるもので、
親子で、どうしてもイライラしてしまう場合は、『一旦離れる』のが、効果的です。
根本的な解決方法にはなりませんが、お互いが怒って衝突するより全然良いですし、ストレス値も下がります。
よく「人の怒りは6秒がピーク」と言われますが、その場から離れることで、怒りをある程度、下げる効果はあります。
イライラの鎮め方については、【6秒で怒りがおさまらない】怒りのタイプ別!7つの対処法 をご覧ください。
個人差はありますが、実際にされてきた方は、「怒る回数は減った」「衝突する頻度が減った」という方が多いです。
発達障害の子の「長期的な勉強イライラ対策」

ここでは、今より勉強がスムーズになる「長期的的な対策」を4つ、お伝えします。
短期的な対処法だけでは、親御さんが疲弊してしまいますし、お子さんの特性に合わせるという点で、専門的な領域にも入り、難易度が高めだと思います。
そういった理由から、第三者の力を借りるのがお勧めになります。
①:民間療育
②:学習塾
③:家庭教師
④:タブレット学習
民間療育
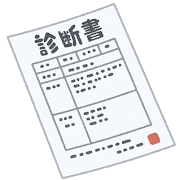
療育とは、発達支援の専門家が、お子さんに必要なスキル獲得を働きかける場所になります。
そして、親御さんがお子さんへの関わり方を学ぶ場にもなります。
療育には、福祉サービスと民間療育の2種類がありますが、ここでは民間療育をお勧めします。
福祉サービスは、通所受給者証が必要になり、手続きに時間がかかる上、混み合っている為、すぐに問題にアプローチするのは難しいです(数か月~数年待ちが多い)。
民間療育ですと、個別指導で、比較的すぐに利用できる上に、1回の利用からできます。
お子さんのタイプにもよりますが『本人の特性把握、家庭でできる学習方法』を教えてもらうだけでしたら、1回の指導でも十分な場合が多いです。
家庭で試行錯誤されても、1か月以上進展が見られない場合は、療育先への相談をお勧めします(相談が早すぎて悪いことはない為)。
学習塾

個別・集団の形態がある、一般的な学習塾になります。
学校の授業に大きな遅れが見られない様でしたら、集団でも大丈夫だと思います。
もし、授業に遅れている場合は、個別の塾の方が良いでしょう。
全体像としては、こちらのイメージになります。
集団の塾が合うタイプ
・友達がいる方がモチベーションが上がる
・周りに刺激を受けて、危機感が出る
(自分事になる)
・費用を抑えたい
個別の塾が合うタイプ
・自分のペースで勉強したい子
・集団だと緊張して質問ができない
・学校の勉強より遅れている子
家庭教師

プロの家庭教師に任せるのも、1つです。
最近は、“発達障害を専門とした家庭教師” も増えてます。
専門的な知識がある先生なら、お子様の特性に合わせて教え方も、工夫してくれます。
ただ、学習塾と比べて、費用は高いので、その点も確認しながら、1つの選択肢として、検討されるのが良いと思います。
私が支援していた子が、実際に利用されていた家庭教師を載せておきますね。
発達障害の子に向けたコースもあり、オンラインも実施しています。
一般の学習塾・家庭教師より、お子さんが理解しやすいのは、言うまでもありません。
ただ、合うかどうかは、お子さんによりますので、
実際にお子さんに体験してもらい、お子さんの感想を聞くことが、一番早く確実だと思います。
実際の先生が無料体験をしてますので、お子さんとの相性を見るのも1つになります。
タブレット学習
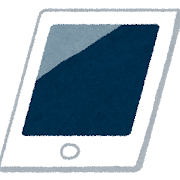
家で出来ることから始めたい!というには、タブレット学習がお勧めになります。
アニメーション・音声・動画など、”お子さんの特性に合わせた豊富な学び方” があります。
学校・学習塾で理解が難しかった子の、一番の理由は、学び方が合っていないことです。
通常のプリント学習だけでは、不十分だからです。
タブレット学習のメリット・デメリットなど詳細は、こちらの記事をご覧ください。
発達障害の有無に関わらず、学習面の困りを抱えた子に共通する内容になります。
1つの学習対策として、参考になれば幸いです。
✅「勉強以外の時間」の確保も大切
勉強しない子に対して、多くのママ・パパは「勉強する場面」にのみ、目が行きがちです。
ただ、勉強以外の時間の過ごし方も、実は勉強には影響します。
特に発達障害の子は、日頃怒られたり、失敗体験が多く、自信を失う機会が多いです。
表面上は分からなくても、溜め込んでいる子も少なくありません。
日頃のストレスや不安などが溜まった状態より、ある程度解消できていた方が、勉強はしやすいです。
あくまで、補助的な効果になりますが、とても大切なことです。
働いている方に休み(リスレッシュ)があるのと同じで、お子さんにも休みが必要です(育児に休みはありませんが…)。
勉強の時間と同時に、「お子さん自身が休める・自由に過ごせる時間」を確保していくことも大切になります。
時々、習い事がぎっしりでストレス過多になっている子もいます。1日のお子様の過ごし方を振り返るのも、1つだと思います。
発達障害の子の勉強が捗る「役立ちアイテム」
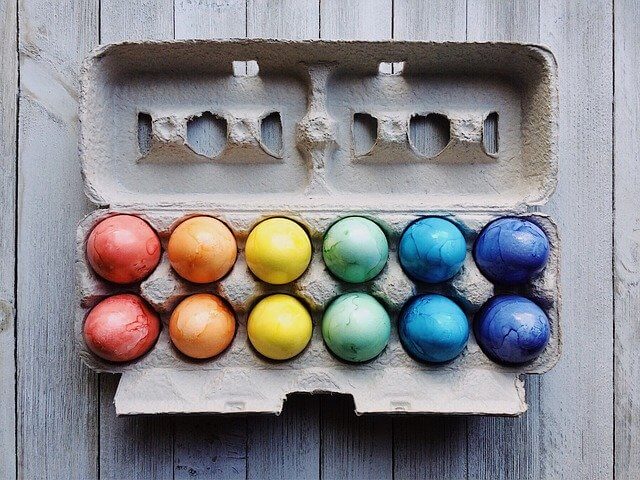
ここでは、私が学習支援でお子さんに使っていただいている、2つのアイテムを紹介します。
下記に該当するお子さんでしたら、役に立つと思います。
・音が気になって集中しづらい
・姿勢がすぐに崩れる
他にも種類はありますので、参考程度にご覧ください。
音が気になって集中しづらい子
※音に敏感で集中しづらい/些細な音が気になる子向け
姿勢が崩れやすい子
※姿勢が崩れやすい/体を揺らしたり落ち着かない子向け
【親子イライラ 発達障害の子の勉強法】まとめ

記事のポイントになります。
✅発達障害の子が勉強で
「イライラする原因」
・勉強をやりたくない
・勉強が分からない
・勉強以外にやりたいことがある
・集中しづらい環境
✅発達障害の子の
「短期的な勉強対策」
・今日のゴールを視覚化する
・勉強の後の楽しみを決めておく
・勉強を妨げる要素をなくす
・本人の得意な学び方に合わせる
✅発達障害の子の
「長期的な勉強対策」
・民間療育
・学習塾
・家庭教師
・タブレット学習
✅勉強が捗る
「役立ちアイテム」
・イヤーマフ(音を遮る)
・ピントスクール(姿勢を正す)
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】









































[…] 【親も子もイライラ】発達障害の子の勉強がスムーズになる4つの対処法 […]
[…] 【親も子もイライラ】発達障害の子の勉強がスムーズになる4つの対処法 […]
[…] 【発達障害の子の勉強】スムーズになる4つの対処法 […]
[…] 【親も子もイライラ】発達障害の子の勉強がスムーズになる4つの対処法 […]