

担任の先生で悩まれてる方「子どもが不登校で相談したいのに、担任の先生が何もしない。どうすればいい?」
お子さんにとって、担任の先生の存在は、とても大きな存在です。
特に、不登校のお子さんでしたら、担任の理解・配慮は、必要不可欠になります。
ただ実際には、担任が何もしてくれなくて、悩まれてるお子さん、親御さんは少なくありません。
そこで本記事では、担任とのやりとりで役に立つ情報をまとめました。
私は、療育・相談支援を15年以上しており、不登校/発達障害の子と親御さんの支援に携わってきました。
担任に関するご相談も多く受けたり、中には、担任の先生とお話をさせていただくこともありました。
その支援経験を元に、本記事をまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
不登校の子へ「担任が何もしない原因」
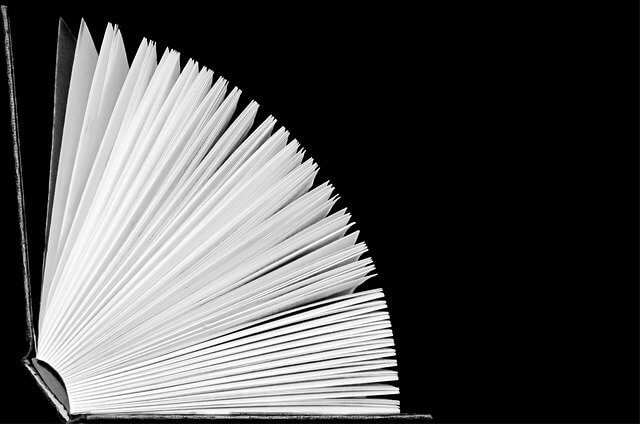
不登校で困ってるのに「担任が何もしない原因」は、主に3つになります。
①:子どもの「特性への理解」がない
②:「先生のスタンス」を変えない
③:先生自身に「余裕」がない
子どもの特性への理解がない
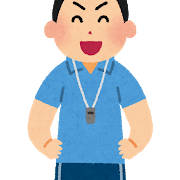
不登校には、当然理由があります。
その理由の1つに、お子さんの特性があります。
・集団の場が怖い
・担任の先生が怖い
・勉強がやりたくない
・人の気持ちを考えすぎ、疲弊してしまう
・周囲の人の矛盾が許せない、イライラする
・先生に怒られてる子を見ると、自分も怒られてる様に感じる
障害特性(発達障害)/育ってきた環境/感じ方/考え方など、お子さんには、様々な “違い” があります。
“違い” 自体に、良い悪いはないのですが、先生自身に、この “違い(特性)” への理解がない場合があります。
「普通は、○○」
「皆は、ちゃんとやってる」
「一人だけ、特別扱いはできない」
などの考えが強く、結果として、何もせず、お子さん・親御さんが辛い思いをしてしまいます。
先生のスタンスを曲げない

教員としての経験を、ある程度積んでいて、自身のスタイルが固まってる分、
柔軟に対応する(新しい視点を入れる)ことが、難しいことがあります。
特に、ベテランの先生(中堅以降)に多いです。
「自分の指導が正しい」
「子どもには、○○すべき」
という気持ちが強く、結果として協力が得られない(相談に応えてもらえない)ことが多いです。
先生自身に余裕がない

経験が浅かったり、対応できる範囲が限られていて、先生自身が教室運営で精一杯な状態のときです。
先生自身に余裕がない為、最低限の教室運営のみで、”プラスαの子どもへの配慮” はありません。
親御さんからお伝えしても、漏れていたり、形だけになり中身が伴ってない場合も、珍しくありません。
担任が何もしない時の「対策」

担任が何もしない時の「対策」は、大きく2つになります。
①:「子どもの特性」を伝える
(原因①:特性理解がない)
②:スクールカウンセラー⇨管理職に相談
(原因②:先生がスタンスを変えない)
(原因③:先生自身に余裕がない)
子どもの特性を伝える

まず、担任の先生と個別面談の時間を設けます。
担任との定期的な面談はあると思いますが、タイミング的に時期がズレていたら、先生に個別で時間をいただくこともできます。
「お忙しい所申し訳ないのですが、子どものことについて個別で相談させていただきたいことがあります。30分ほどお時間をいただくことは可能でしょうか」
のようにお伝えするイメージで、相談をしてみます。
面談でお話できることになったら、お子さんが困ってる場面をお伝えします。
例えば「子どもが学校に行きたがらなくて、クラスにいると疲れちゃうって言ってるんです」とお伝えし、クラスの何に疲れるのかなど、可能な範囲で詳細をお伝えします。
先生に内容が伝わることで、
「学校で、できることを考えてみます」
「他の部屋が使えるか、確認してみますね」
「放課後課題だけ取りに来てみますか?」
など、先生に反応があるかもしれません。
検査結果を渡すのも1つ
療育・医療機関などに繋がってる方は、検査結果など、本人の様子がわかる記録(控え)を渡すのも1つです。
先生によっては、専門の方からの意見があれば、説得力が増し、協力に繋がる可能性もあるためです。
あと「学校と共通認識をもつ」という意味でも大事になってきます。
スクールカウンセラー→管理職に相談

担任の先生に、相談に応じてもらえない場合になります。
そんな時は、担任以外で、下の役割を持つ先生に相談することをお勧めします。
・スクールカウンセラー
・学校の管理職
(ex.校長、副校長、教頭)
スクールカウンセラーは、学校・ご家庭の間に立つ先生(中立に近い立場)になります。
お子さんのことは勿論、担任の先生とのやりとりなども含めて、学校生活全般の相談ができます。
スクールカウンセラーは、非常勤として週に数日勤務してる場合が多いです。事前に面談を申し込み、個別相談することができます。
もう1つの方法として、管理職の先生への相談です。
学校として協力が得られないか、どのような方法なら可能なのかなど、相談をします。
ご両親で参加できる場合は、その方が状況を客観的に判断しやすくなる為、学校との共通認識を持ちやすくなると思います。
【関連記事】
【別室登校の過ごし方】メリット/デメリット/教室へ復帰する5つのポイント
担任とやりとりする上で「大切なポイント」

担任(学校)とやりとりする上で「大切なポイント」は、3つになります。
①:「担任/学校と対立」は避ける
②:「学校側の味方」を一人作る
③:「お願い<相談」のスタンス
担任/学校と対立は避ける

これが一番基本的で、大事なスタンスになります。
担任の先生、学校側との対立は避けることです。
対立したくなる気持ちは、とても理解できるのですが、対立した所で、そのしわ寄せは、最終的にお子さんにいきます。
お子さんの学校での過ごしやすさを作る為にも、これから学校と相談を重ねて協力していく為にも、
学校との関係性は、とても大事になります。
学校側の味方を一人作る
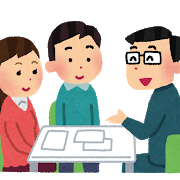
一人で良いので、学校にいる先生の中で、味方を作ることが大切になります。
これができると、親御さんの相談先がある安心感に繋がりますし、
お子さんとしても「学校には、話ができる○○先生がいる」となる為、学校のイメージが違ってきます。
信頼できる先生が一人いるかどうか、これはお子さんからしたら、大きな違いになります。
もし、信頼できる先生がいましたら、その先生を窓口に、学校と相談するのが良いと思います。
信頼できる先生が、担任/スクールカウンセラーでない場合でも、
学校との面談で、同席をお願いすることもできます(応じてもらえるかは、学校次第になりますが)
私が知る事例では、実際に立ち会ってもらい面談をされた方もいました。
お願い<相談 のスタンス
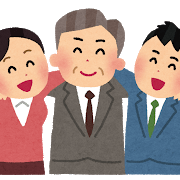
親御さんのスタンスは、あくまで「相談」ベースであることが大切になります。
少しでも多くのことを、少しでも早くお願いしたい気持ちは、とても分かります。
ただ、一方的な”お願い” になると、協力が得づらくなるのも事実です。
誰でも、一方的にお願いされることは、良い気持ちはしません。協力してもらえたとしても、表面的なものになってしまうかもしれません。
先生の気持ち、教室の状況などを聞いて、
先生が、
・精神的
(必要性を感じてる/納得感がある)
・物理的
(時間がある/体力的にできる)
に、どんな方法なら協力が可能か、一緒に見つけていくことが大切になります。
【不登校の対策 担任が何もしない時】まとめ

記事のポイントになります。
✅不登校で困ってるのに
「担任が何もしない原因」
・子どもの「特性への理解」がない
・「先生のスタンス」を変えない
・先生自身に「余裕」がない
✅担任が何もしない時の
「対策」
・子どもの特性を伝える
・スクールカウンセラー/管理職に相談
✅担任とやりとりする上で
「大切なポイント」
・担任(学校)と対立は避ける
・学校側の味方を一人作る
・「お願い<相談」のスタンス
✅不登校の子が
「備えたいこと」~担任の協力が得られない時~
・学習の成功体験
・特性に合う学習法
・レベルに合う学習単元
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、お役に立てば幸いです。
【関連記事】
【不登校の母親】今より気持ちを軽くする4つの過ごし方/5つの視点








































[…] 【担任が何もしない】不登校の子が困らない為の3つの対策 […]
[…] 【担任が何もしない】不登校の子が困らない為に。3つの対策・大切なポイント […]
[…] 【担任が何もしない】不登校の子が困らない為の3つの対策 […]
[…] 【担任が何もしない】不登校の子が困らない為に~3つの対策・大切なポイント~ […]
[…] 【担任が何もしない】不登校の子が困らない為の3つの対策 […]