

子どもの不登校で悩まれてる方「不登校の子の親は、問題にどう向き合って乗り越えればいいの?乗り越え方/事例も教えてほしい」
「イライラ、不安、無気力、無関心、食欲低下、睡眠不足…」
不登校の問題は、お子さんだけでなく、家族にも大きな負担を掛け、ときに追い詰めてしまうものです。
この記事を執筆してる私は、発達・相談支援を15年以上しています。
今まで、多くの不登校の子・親御さんへの支援もさせて頂きました。
その経験を通して感じたのは、お子さんは勿論、親御さんの支援も大事ということ。
精神的に追い詰められ、ノイローゼ気味になる方を、何人も見てきました。
そこで本記事では、「親御さんがノイローゼになる前に、押さえておきたいこと」をまとめました。
お子さんの不登校で悩まれてる方の、お役に立てば幸いです。
目次
不登校は「親のメンタル」が最重要

まず最初にお伝えしたいのは、不登校の問題は、お子さんは勿論ですが、
「親のメンタル」が、最も重要だということです。
なぜなら、不登校の子には、心を休ませる時間が必要で、その為には、家で過ごす安心感が大切になるからです。
本人の “家で過ごす安心感” を作る為には、一緒に過ごす「家族の心身の健康」が不可欠です。
親御さんが疲弊していたり、不安定な気持ちが続いてると、表情や態度・雰囲気から、お子さんは察します。
家で安心して過ごせず、次第に自分の殻に閉じこもっていきます。その分、不登校で辛い思いをする期間が長くなりやすいです。
親のメンタルを守る為に「大切なこと」

ここでは、親のメンタルを守る為に「大切なこと」を5つお伝えします。
試したことがなければ、ぜひ参考にしてみて下さい。
①:不登校児の状態を「知る」
②:信頼できる人に「話をきいてもらう」
③:「支援先」に繋がる
④:「経験者の話」を聞く
⑤:学習の心配は「タブレット学習」を導入
不登校児の状態を知る
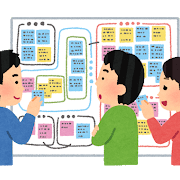
まず最初に、“不登校の子の状態” を把握することが大切になります。
不登校には、段階があります。その段階によって “お子さんに必要な関わり/配慮” は、変わってきます。
ここの把握が難しいと、お子さんの状態に合わない関わりをして、逆効果になる場合があります。
実際の不登校ケースでは、親御さんが良かれと思った関わりが、
かえってお子さんを追い詰めてしまい、問題の解決が難しくなることも、少なくありません。
そういった理由から、こちらの2点を始めることが必要になります。
・不登校の子の状態を把握する
・これからどんな関わり/配慮が必要か
不登校のお子さんの状態は、こちらの記事にまとめてます。
「不登校の状態って何?」という方は、ご覧ください。
【関連記事】
信頼できる人に話をきいてもらう

当たり前ですが、とても大切なことです。
今抱えてる不安・ストレスを、言葉にして人に聞いてもらうだけで、ストレス値が下がる方は多いです。
ただ、「相談できる人がいない」という方もいらっしゃると思います。
そういう方には、このあと説明する
「支援先に繋がる」
「SNSを活用する」
という方法もあります。次の項で、説明したいと思います。
支援先に繋がる

家族や学校だけで、問題の解決が難しい場合は、支援先(専門機関)に繋がることを、お勧めします。
・家庭以外の安心できる場所
・学校以外での繋がり
・困ったら “アドバイスがもらえる状態”
これらを作る目的から、支援先と繋がるのは、効果的になります。
支援先の例としては、スクールカウンセラー、支援コーディネーター、お住まいの役所の窓口(福祉課)、児童相談所などがあります。
中には、通級/支援級の先生に相談される方もいます。
本人も繋がれれば理想ですが、それが難しい場合は、
まずは、親御さんが相談にいき、話を聞いてもらう所から始めても大丈夫です。
経験者の話を聞く

不登校の子を育てた先輩ママ・パパに、話を聞くのも1つです。
親戚や近所にいれば、話を聞いてみましょう。
もし、身近に聞ける人がいない場合は、1つの方法として、SNSがあります。
SNSでは、不登校や発達障害など、お子さんの育児で悩まれてる方が、沢山いらっしゃいます。
経験談・考えなどを発信される方もいれば、お互い労って支え合ってる方もいます。
SNSですので、本音で話ができ、ご近所ならではの気遣いも不要です。
「全く情報がない」「色んな方の経験談が知りたい」という方には、お勧めになります。
学習の心配はタブレット学習を導入
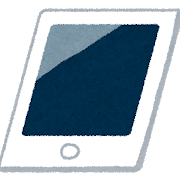
不登校問題で、親御さんの心労の1つが「学習の遅れ」です。
授業に参加できない⇨学習が遅れる⇨進路の選択肢が少なくなる
という心配が、常にあります。
また家で勉強するにしても、親御さんが日中仕事で様子が見れず、勉強が十分にできているか、把握しきれないケースも多いです。
親御さんが教えようとしても、本人の癇癪に繋がり、親御さんと衝突することも少なくありません。
家庭学習に難しさを感じてる方には、1つの方法として「タブレット学習」があります。
不登校の子が、タブレット学習を使うメリットは、下記になります。
・家庭内で出来る
・一人で出来る
・遠隔で親が把握できる
・出席扱いになる場合がある
「塾に通わせたいけど、外に出たがらない」
「子どもに勉強を教える時間がない」
「学習の遅れが心配(ストレス)」
という方には、1つの選択肢になります。
本記事の後半で、改めて不登校の子の学習対策が大切な理由をお伝えします。
具体的なタブレット学習の種類を把握されたい方は、こちらの記事をご覧ください。
発達障害に関わらず、学習に困りがある子に参考になる内容になっています。
不登校の子/親の「事例」

ここでは、不登校の子/親の「事例」についてお伝えします。
私の支援経験の範囲内ですと、大きく分けると3つのパターンに分かれます。
あくまで、私が支援してきた子の事例になりますので、参考程度にご覧下さい。
①:「支援先」に繋がる
⇨フリースクール/通信制高校
②:家庭で「休養」
⇨少しずつ学校へ登校
③:「精神的に不安定」になる
⇨クリニックに通院
支援を受ける⇨フリースクール/通信制高校
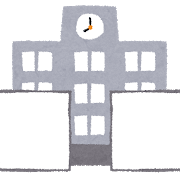
不登校期間が数ヶ月以上続き、学校に行ける気配がない方は、
支援先に相談される場合が多いです。
支援先とは、主に民間療育になります(福祉サービスは混み合っていて、実質利用できないことが多い)。
お子さんが気持ちを話したり、生活の振り返り/今後頑張りたいことなど、対話などを通して、一緒に話をする内容になります。
本人から出た「今後頑張りたいこと」に繋げる為に、フリースクールや通信制の高校に通う子がいます。
ここで大切なのは、「フリースクール/通信制高校に行く」が目的にならないことです。
お子さんが将来やりたいこと、これから学びたいことを実現する為の手段として、
「フリースクール/通信制高校に行く」のイメージになります。
ここの認識がズレると、新しい学校に通ったけれども、途中で行きたくなくなった、など後から困ってしまうことになります。
✅「転校」も1つの方法
「在籍校がどうしても合わない」という方の中には、稀に転校される方がいます。
在籍校との関係性が悪かったり、別の学校の校長先生の考え/学校方針などに共感できて、
そこの学校に通う為に、引っ越しをされる場合があります。
家庭で休養⇨少しずつ学校へ登校
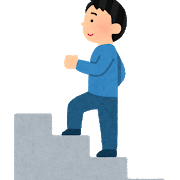
不登校の子には、よく「充電期間が必要」と言われます。
ここでは、深くは触れませんが、
不登校の子は、心に負った傷を回復させる時間が必要になります。
その為に家でゆっくり休みます。回復してくると、次第に本人の意識が外に向きます。
これが、「保健室登校」や「放課後に担任に話に行く」などに繋がります。
少しずつ、学校で過ごせる時間が増え、保健室で過ごしていたのが、
教室で過ごせる様になったり、学校で過ごせる時間が増えてきます。
周囲の大人が、不登校の子への理解を深め、声掛けをすることが、大切になります。
不登校の子への “具体的な声の掛け方” は、こちらの記事をご覧ください。
【不登校の子ども】何が正解なの?望ましい声かけ/避けたい声かけ
精神的に不安定になる⇨クリニックに通院

不登校が理由で、叱責されたり、無理やり学校に行かされたりと、
辛い経験を重ね続けることで、「精神的に不安定」になる子がいます。
具体的な様子としては、
・無気力
・引きこもり
・情緒不安定
など、日常生活・社会生活に大きな支障が出る状態です。
この場合は、医療機関、児童相談所などの専門機関に繋がり、
本人の心身の安定を作ることに、専念する必要があります。
【ノイローゼ予防 不登校の親の気持ち】まとめ

記事のポイントになります。
✅不登校は
「親のメンタルが最重要」
・親自身のことも大切にする
・”学校に行く” を目的にしない
✅親のメンタルを守る為に
「大切なこと」
・不登校児の状態を知る
・信頼できる人に、話をきいてもらう
・支援先に繋がる
・経験者の話を聞く
・学習の心配は、タブレット学習を導入
✅不登校の子/親の
「事例」
・支援先⇨フリースクール・通信制高校
・家庭で休養⇨少しずつ学校へ登校
・精神的に不安定になる⇨クリニック
✅不登校の子/親が
「備えたいこと」
・学習の成功体験
・学習習慣の定着
・特性に合う学習法
・レベルに合う学習法
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】
【不登校の子は勉強追いつくの?】学習支援でも実践してる6つの勉強法









































[…] 【不登校の親】ノイローゼになる前に。親のメンタルを守る為に大切なこと […]
[…] 【不登校の親】ノイローゼになる前に。親のメンタルを守る為に大切なこと […]
[…] 【不登校の親】ノイローゼになる前に。親のメンタルを守る為に大切なこと […]