

子どもに合う絵本を探してる方「発達障害の子に合う絵本ってあるのかな。おすすめの絵本を教えてほしい」
「子どもが絵本に興味を持たない…」
「興味の幅や言葉を学んでほしい…」
発達障害(ADHD/自閉症)のお子さんは、興味・関心の偏りが大きかったり、関心の幅が、極端に狭いことが多いです。
本記事を読まれてる親御さんの中には「絵本を楽しめたり、そこから言葉の発達など成長に繋げてあげたい」と思われる方も多いと思います。
そこで本記事では「発達障害(ADHD/自閉症)の子におすすめな絵本」について、お伝えしたいと思います。
この記事の執筆者の私は、療育・相談支援を15年以上しており、
発達障害のお子さん・親御さんの支援をしてきました。
その支援経験を元に、本記事をまとめています。参考になれば幸いです。
※現在は、自閉症ではなく「自閉スペクトラム症(ASD)」と総称されています。本記事では、説明の都合、「自閉症」と表現しています
発達障害の子に「おすすめな絵本13冊」
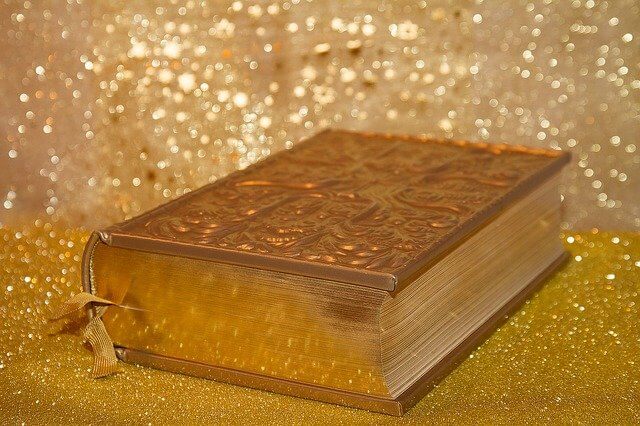
発達障害の子に「おすすめな絵本」を13冊お伝えします。
絵本の好みは、個人差がありますので、絵本探しの材料として、ご覧ください。
「通常の絵本」
「手触りを楽しめる絵本」
「音を楽しむ絵本」
など、”様々な楽しみ方ができる絵本” をまとめてます。
①:だるまさんシリーズ
- イラスト/展開がシンプル
- 分かりやすく、楽しみやすい
- 特性に関わらず、好きな子が多い
②:もこもこもこ
- シンプルなイラスト
- マネ(音の)しやすい音が多い
- 発声の練習におすすめ
※一般的に、繰り返す音は発しやすい
③:しましまぐるぐる
- 一定のリズムで、集中が切れづらい
- 興味を引きやすいデザイン
④:じゃあじゃあびりびり
- 興味を引く効果音が多い
- 発声しやすい音が多い
- 発声頻度を増やしたい子向け
⑤:あかまる さわって!
- 手触りが楽しめる
- 感覚遊びが好きな子向け
(触感への刺激になる)
⑥:新版 あかまる ぺたっ!
- 貼る/はがす、で楽しめる
- 色/形/大きさの概念理解
(キッカケ作りになる)
⑦:ふわふわだあれ?
- “フワフワした手触り” が好きな子向け
- 絵本に “興味を持つキッカケ” になる
⑧:かたちが ぱぱぱ
- 興味を持つ子が多い
- イラストの形が変わる絵本
- 視覚的に楽しめる
(色/イラスト/動き)
⑨:ドアをあけたら
- 展開がシンプル
- ドアの開閉後の変化を楽しむ
⑩:まるまる ころころ
- “様々な変化” が楽しめる絵本
- “注意を引く変化(工夫)” が多い
⑪:おとのでる♪のりものえほん
- “絵本に興味を持つ” キッカケ作り
- “乗り物好きな子” におすすめ
⑫:たのしいてあそびうた
- 聞いて楽しむことが多い子向け
- 手遊びに “興味を持つキッカケ” になる
⑬:アンパンマン ことばずかん
- 言葉に興味を持つ “キッカケ作り”
- “絵本に興味を持ちにくい子” にお勧め
- “タッチペン” で興味を持つ子も多い
【合わせて読みたい記事】
絵本を選ぶ時の「3つのポイント」

発達障害の子の「絵本を選ぶ時の3つのポイント」をお伝えします。
①:絵/色/音が「シンプル」
②:「直感的」に楽しめる
(視覚/聴覚/触覚)
③:「1P完結」の内容
絵/色/音がシンプル
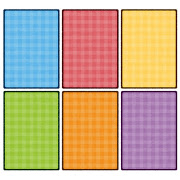
イラスト/色がシンプルな方が、見やすく、興味を引きやすいです。
“感覚的に楽しめるデザイン” の方が、見てくれる子が多いです。
直感的に楽しめる

発達障害の子の中には、感覚遊び(五感)が好きな子が多いです。
理由は、ゆっくりな発達段階・感覚の偏りなどになります。
特に絵本では、下の感覚を楽しんでる子が多いです。
・視覚
(絵/動き/絵の変化)
・聴覚
(音、声の大小/スピード)
・触覚
(手触り)
1P完結 の内容

発達障害の子は、自分の好きなもの以外に、
関心を寄せたり、集中力を持続させることが難しいです。
そのため、結果が直感的に分かる絵本の方が良いです。
1P完結のタイプで、そのページ毎に楽しめる内容の方が、合ってる子が多いです。
【関連記事】
読み聞かせの「4つのコツ」
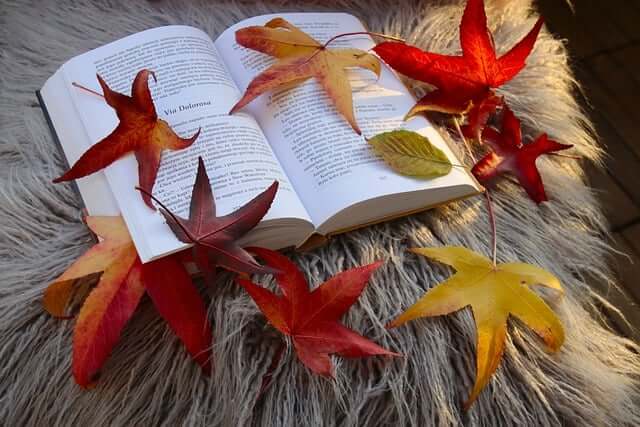
発達障害の子への「読み聞かせのコツ」は、4つあります。
実際の支援の現場でも、実践されてる内容になります。
①:「短く・はっきり・テンポ良く」読む
②:「変化」をつける
③:「絵に合わせて」音を出す
④:絵本の「仕掛け」を活用する
短く・はっきり・テンポ良く 読む
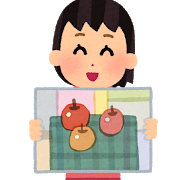
先ほども触れましたが、発達障害の子は、”絵本に集中できる時間” が、限られてることが多いです。
そのため、1つ1つは「短く・分かりやすく・集中が切れる前に、次の展開に進める(変化をつける)」必要があります。
絵本の文章は、発達障害の子にとって長いものもあります。
ちょっとした物語の絵本でしたら、文章をそのまま読むのではなく、
その子の集中力が切れない程度に、文章を短くする方が良いです。
物語にそこまで影響が出ない文を飛ばしたり、短くするイメージになります。
これは慣れていないと、難しいかもしれませんが、
イラストを見ながら(文章はあまり見ず)読み上げる文章を考え、読み聞かせするイメージになります。
お子さんに聞いてほしい音(ex.効果音・繰り返し音・名詞・動詞・人物)を中心に読み上げるのも、
おすすめの読み聞かせになります。
変化 をつける

発達障害の子は、視覚的に楽しんでることが多いです。
そのため、絵本ですと、イラストの変化/動きの変化など、視覚的に楽しめる様に働きかけると効果的です。
逆にいうと、絵が変わらなかったり、展開が遅いと、視覚的な楽しみ(変化)が感じづらくなるので、興味を持たれません。
発達障害の子が絵本に興味を持ちづらい理由の1つとして、直接的な感覚刺激を受けづらい点にあります。
回ったり、飛び跳ねたり、手触りだったり、感覚を楽しむ段階の子にとっては、絵本は楽しみを見出しづらいのです。
そのため、絵本の中ですと、イラスト/動きに変化をつけて、視覚的に楽しめる様に読み聞かせの工夫をする必要になります。
絵本を使った具体的な “変化のつけ方” は、下のような工夫例があります。
・ 声の強弱/抑揚
・読むスピードの調節
・ページのめくり方
・表情/動きを変える
・読み手の動きの変化
“変化をつけて読む” ことで、興味を引きやすくなります。
絵に合わせて音を出す

言葉の理解に繋げていく為に、
絵本のイラストに合わせて、音(効果音・物の名前・動作など)をつけると効果的になります。
すぐに “言葉” に繋がるわけではありませんが、
積み重ねていくことで「赤くて丸い物⇨りんご」のように、次第に理解が繋がっていきます。
これは絵本に限らず、日常生活の中でもできると良い関わりになります。
絵本の 仕掛け を活用する

発達障害の子は、通常の絵本だけでは興味を持ちづらいことが多いです。
そのため、“興味が持てる要素のある絵本” を選ぶ必要があります。
その1つが「仕掛け絵本・音が出る絵本」になります。
イラストだけの絵本は「見る(視覚)」と「聞く(聴覚)」が中心ですが、
仕掛け絵本の場合は、
手触り(触覚)や、仕掛けの変化(より強い視覚)があります。
音絵本の場合は、
電子音・歌など、読み手には、出しにくい音(聴覚)が出せます。
このように、お子さんが好む感覚・刺激が多い絵本を選んでいきます。
【合わせて読みたい記事】
【発達障害の子向け おすすめ絵本13冊】まとめ

記事のポイントになります。
✅発達障害の子に
「おすすめな絵本13冊」
・だるまさんシリーズ
・もこもこもこ
・しましまぐるぐる
・じゃあじゃあびりびり
・あかまる さわって!
・新版 あかまる ぺたっ!
・ふわふわだあれ?
・かたちが ぱぱぱ
・ドアをあけたら
・まるまる ころころ
・おとのでる♪のりものえほん
・たのしいてあそびうた
・アンパンマン ことばずかん
✅絵本を選ぶ時の
「3つのポイント」
・絵/色/音がシンプル
・直感的に楽しめる
・1P完結型
✅読み聞かせの
「4つのコツ」
・短く/はっきり/テンポ良く読む
・変化をつける
・絵に合わせて音を出す
・絵本の仕掛けを活用する
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】







































[…] 【療育指導員が厳選】ADHDの子供にオススメな絵本5冊【ADHDが学べる絵本5冊も紹介!】 […]
[…] 【ADHDかも?と思ったら】おすすめな絵本5冊と読み聞かせの工夫を紹介 […]
[…] 【ADHDかも?と思ったら】おすすめな絵本5冊と読み聞かせの工夫を紹介 […]
[…] 【ADHDかも?と思ったら】おすすめな絵本5冊と読み聞かせの工夫を紹介 […]
[…] […]
[…] 【発達相談員がおすすめ】発達障害の子が楽しめる絵本~厳選10冊の紹介~ […]
[…] […]
[…] […]
[…] 【発達相談員がおすすめ】発達障害の子が楽しめる絵本 10冊 […]
[…] 【発達障害の子向け】おすすめ絵本13冊 […]
[…] 【発達障害の子向け】おすすめ絵本13冊 […]