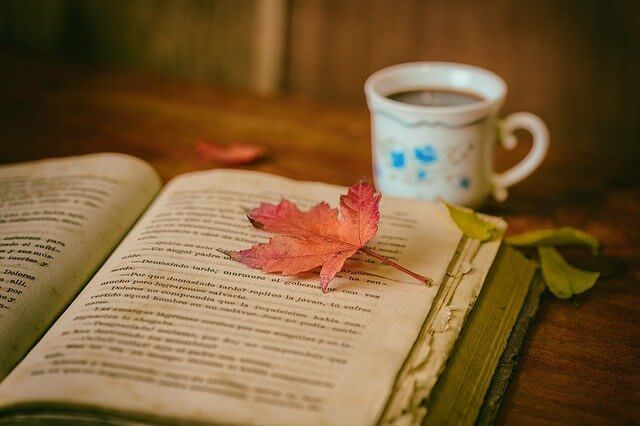

発達障害の本を探してる方「発達障害がわかりやすく解説されてる本が知りたい。子どもへの関わり方など、本で学びたい」
以前に比べると、「発達障害」という言葉を耳にする機会は増えました。
ただ、聞く機会は増えても、
「発達障害って言葉は知ってるけど、どんな特徴があるの?」
「子どもに具体的に、どう関わればいいの?」
と悩まれてる方は、少なくないと思います。
そこで本記事では、目的別に「発達障害の解説がわかりやすい本」についてお伝えしたいと思います。
この記事の執筆者の私は、療育支援/発達相談員を15年以上しており、
発達障害のお子さん・親御さんの支援に携わってきました。
その支援経験を元に、本記事をまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
発達障害が「わかりやすい本」~基礎知識~

発達障害の「基礎知識が学べる本」を2冊お伝えします。
①:発達障害の子どもの心がわかる本
- “乳幼児~小6” の子が中心
- 発達障害の基礎知識
- ADHD,ASD,LDの基礎知識
②:発達障害の子供の心と行動がわかる本
- 発達障害が網羅的に学べる
- 具体的な生活場面に合わせた手立て
【関連記事】
発達障害が「わかりやすい本」~関わり方~
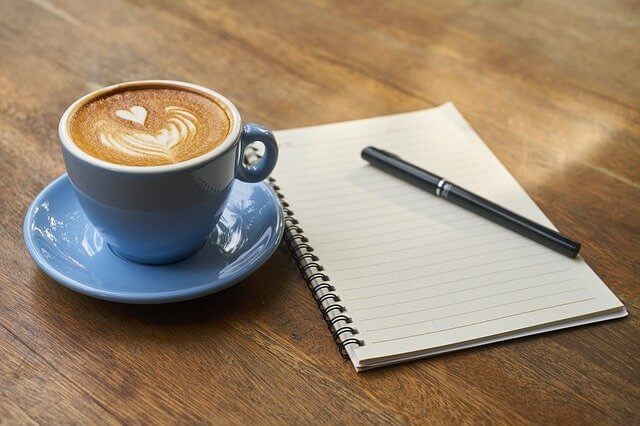
発達障害の子の「家での関わり方」が学べる本を4冊お伝えします。
①:魔法の言葉かけ
- ABA(応用行動分析)を元に構成
- 具体的な声掛け等、実践しやすい内容
- 体系的にまとまっていて汎用性が高い
②:発達障害の子の育て方
- 親が持ちたい “心構え” が学べる
- リアルな “発達障害児の育児” が知れる
③:発達障害/グレーゾーンの小学生育て方
- “小学校生活の困りの解消” がテーマ
- “すぐに使える手立て” が学べる
- “親の体験談(事例)” が知れる
④: 伝わる!声かけ変換
- 言葉のポジティブ変換が学べる
- 場面毎に使える具体的な声掛け
- 肯定的な声掛けが思いつかない方向け
【関連記事】
発達障害が「わかりやすい本」~手立て~

「発達障害の知識・手立てを更に深めたい方」向けに5冊お伝えします。
①:声かけ・接し方大全
- 手立てを、沢山学びたい方向け
- 困りの具体的場面に合わせた手立て
②:ABAトレーニング
- 理論として理解できる
- 体系立てられた視点、関わりが学べる
③:発達障害の子どもをサポートする本
- 具体的場面での対応法が学べる
- 発達障害の子のチェック項目あり
(参考程度)
④:ADHDの子どもをサポートする本
- 園/学校/医療との連携も学べる
- “典型的な困り場面の対処法” が知れる
⑤:自閉症スペクトラムの子をサポート
- “家庭/園/学校のサポート事例” の紹介
- 社会自立に向けた支援も解説
【関連記事】
【発達障害(グレーゾーン)の本11選】まとめ

記事のポイントになります。
✅発達障害の
「基礎知識が学べる本」
・発達障害の子どもの心がわかる本
・発達障害の子供の心と行動がわかる本
✅発達障害の子の
「関わり方が学べる本」
・魔法の言葉かけ
・発達障害の子の育て方
・発達障害&グレーゾーンの小学生の育て方
・伝わる!声かけ変換
✅発達障害の子への
「手立てを増やす本」
・ 声かけ/接し方大全
・ABAトレーニング
・発達障害の子どもをサポートする本
・ADHDの子どもをサポートする本
・自閉症スペクトラムの子どもをサポートする本
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】








































[…] 【厳選3冊】療育セラピストの私がおすすめのグレーゾーンの子供の本 […]
[…] 【厳選3冊】療育セラピストの私がおすすめのグレーゾーンの子供の本 […]
[…] 【厳選3冊】療育セラピストの私がおすすめのグレーゾーンの子供の本 […]
[…] 【厳選3冊】療育セラピストの私がおすすめのグレーゾーンの子供の本 […]
[…] 【療育支援員がおすすめ】発達障害・グレーゾーンが理解できる本~厳選6冊~ […]
[…] 【療育支援員がオススメ】グレーゾーンの子供が理解できる本・厳選3冊 […]
[…] […]
[…] 【療育支援員がおすすめ】発達障害・グレーゾーンが理解できる本 9冊 […]
[…] 【厳選3冊】オススメのグレーゾーンの子どもの本 […]
[…] 【療育支援員がおすすめ】発達障害・グレーゾーンが理解できる本 9冊 […]
[…] 【発達障害】理解しやすい本11選~3つの目的別に紹介~ […]
[…] 【療育支援員がおすすめ】発達障害(グレーゾーン)が理解しやすい本11選 […]