
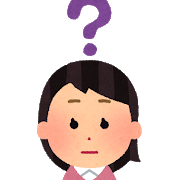
ADHDの子の関わりを知りたい方「ADHDの子どもを理解してあげたい。育児に役立つ本が知りたい。おすすめの本を教えてほしい 」
「療育を受けるほどではないけど、子どもの発達が心配」
「診断は出てないけど、子どもがADHDの傾向がある」
お子さんの発達や接し方で悩まれている方は今、とても増えています。
この記事を執筆している私は、療育支援員を15年以上しています。
その支援経験を元にお伝えします。参考になれば幸いです。
ADHDの子の育児「オススメな本5冊」
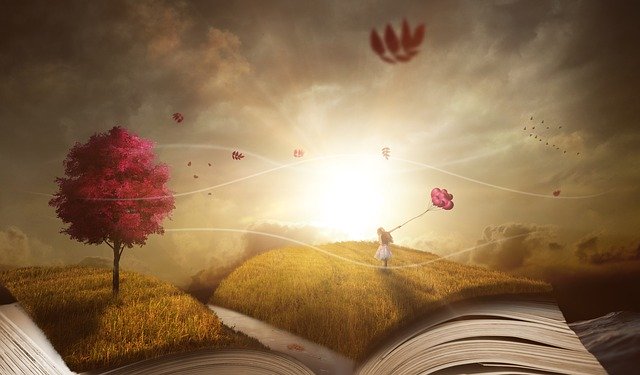
それぞれの本の特徴を、お伝えします。
時間がある方は、紹介する順番に読めると、必要な知識が効率的に身につけられます。
①:ADHDの本
- ADHDの概要が掴める
- 基本的な関わり方が学べる
- 典型例が多く、最初の1冊としておすすめ
②:魔法の言葉かけ
- 発達障害の子全般に使える基礎知識が学べる
- ABA(応用行動分析)を元に根拠が明確で、実践的
- 日常生活の中での実践方法が多く、誰でもすぐ実践できる
③:ADHDの子の育て方のコツがわかる本
- 育児に活かすノウハウが多い
- ①②の本の知識を、この本をプラスで取り入れられると、更に効果的
- 親の視点で執筆されている
④:ADHDのペアレントトレーニング
- “ADHDの子の育児” への向き合い方が学べる
- 親自身のスキルアップができる
⑤:ADHDの子どもたちをサポートする本
- 家庭・学校での配慮方法が具体的に学べる
- 先生にサポートを依頼する時に、そのまま活用できる
- 図も多く、理解しやすい
✅専門書を買う必要はない
理由は、実践が難しいためです。実践ができなければ、本を読む意味は、あまりありません。
ここでいう、専門書とは “学問書” に近いイメージです。
「独立して療育をする・資格をとる」などの理由がない限り、まずは上記で紹介した本を読みながら実践で、十分です。
恐らくほとんどの読者さんは、「専門知識を増やす<子どもに合った関わり方を学ぶ」だと思います。
目的にあった本を選んでいただければと思います。
【合わせて読みたい記事】
本がオススメな「3つの理由」
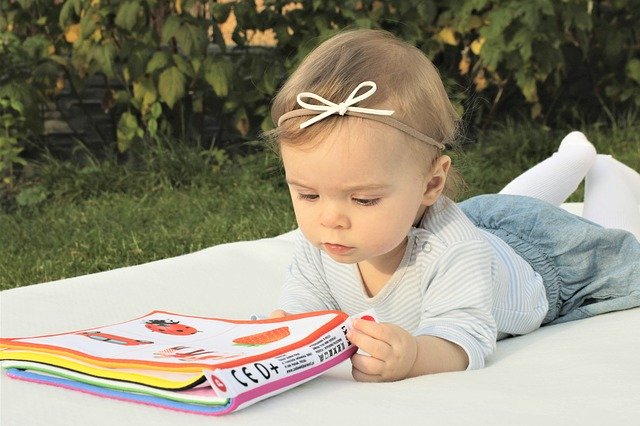
低予算で学べる
療育は毎月の費用がかかります。障害の程度によって様々ですが、
民間の療育ですと、月間で3~7万、自宅への訪問型は、10万以上かかる所があります。
区の療育は混み合っていて、数ヶ月~数年待たれるケースも多いです。
仮に利用ができたとしても、月に数回など、成果が出づらい通い方になりやすいです。
親御さんが学び、家庭内で解消できる場合は、本5冊購入されても、
1万円前後で、療育の1割以下の費用を抑えられます。
ちなみに、家庭内の解消の目安は、
“生活に支障が出るほどの困りが3ヶ月以上出ていない状態” になります。
『周りの子との違いはあるけど、生活で凄く困るわけじゃない』という状態であれば、様子を見守る形で良いと思います。
自分のペースで学べる
仕事や育児で、親御さんは日々大変ですよね。
私も2児の親なので、時間に追われる親の気持ちはよくわかります…。
まとまった時間がないと、必要な量は学びづらいです。そんなときに本が便利です。
家事の合間やちょっとした空き時間を活用できれば、2週間に1冊は読める方も多いと思います。
本記事で紹介する本は、そんな空き時間でサクッと読めるものを選んでいます。
包括的に学べる
本は、決まったテーマを “網羅的に” 学ぶことができます。
例えば、ADHDの特性/親の関わり方/親の体験談など、必要な知識・情報・事例を、まとまりとして、学ぶことができます。
本の知識を生活に活かす「8つの活用法」

本を読むだけでは、子どもの困りは解消されないですよね。
その知識をどう、活かすか?が、重要になります。
今日から実践できるよう、具体的に2つお伝えします。
①:本の知識を1日1回「実践する」
②:本にある配慮を「先生に依頼」する
本の知識を1日1回実践する
具体的な行動で決める

“お子さんへの関わり方”は、具体的行動で決めます。
理由は、実践できたのか?効果があったのか?を、確認するためになります。
「誰が、いつ、どこで、何をする」を決めることが、大切になります。
例えば、母親が子どもを褒める場合(寝る前にオモチャの片付けができたら)
・「全部オモチャを箱に片付けられたね」と褒める:○
・上手に片付けられた時に褒める:✕
表現が抽象的ですと、「何となくできたかな」と、親御さんの自己満足になりやすいです。
1日1回でも良いので、具体的な行動を意識して実践することが大切です。
『実践できた!orできなかった!、を判断できるか…?』
を自問自答しながら考えると、イメージしやすいと思います。
継続できるものにする

具体的な行動で決められても、継続できなければ、あまり効果が期待できません。
必ず、”継続できるイメージの湧くもの” にします。
生活の中で、8割ぐらい出来るようになるまで、続けるのが目安になります。
ex.10回約束した場面があって、8回以上約束が守れた
日常生活の中で、できることにする

親御さんは、育児/お仕事で多忙な毎日を、送っているかと思います。
最初は、張り切って頑張れますが、だんだん失速することが多くなります。
そこで対策として、”日常生活の中でできること” を見つけるのが、おすすめです。
例えばお子さんが、宿題を見せにきてくれた時の声掛けを
「はい。終わったね→全部自分で解けたんだね!凄いね!」
に変える様な、イメージになります。
普段の忙しい生活に、プラスαの関わりは負担になるものです。
成果を出す秘訣は、普段の関わりに1つ、工夫を入れることです。
振り返る

工夫した関わりに効果があった…?
を確認するのが、大切になります。
振り返りの回数は多い方が良いですが、1日1回・1週間に1回など、
継続できる回数を決められるのが一番だと思います。
お子さんの変化を、他の家族に聞いてみるのも、おすすめになります。
効果を確認し、必要に応じて、関わり方を変えていけると良いと思います。
本にある配慮を先生に依頼する
先生のスタンスを把握する

お願いをする前に、”先生のスタンス” を確認します。
お願いしたいことがあっても、先生が協力してくれなければ、意味はありません。
先生が協力してくれる可能性があるのか…?もしくは難しいのか…?ここの確認が大事になります。
私の経験上ですが、傾向としては、経験の浅い若い先生は協力的な方が多めで、
ベテランの先生は、柔軟な対応がむずかしい場合が多いです。
これは先生によりますので、必ず先生と直接お話をしながら、見極めたいところです。
見極める方法として、”先輩ママ” に聞くことも1つになります。
先生がどう感じているか、把握する

先生自身が必要性を感じないと、協力してもらえません。
先生が必要性を感じていない場合は、協力をお願いする前に、子どもが何で困っているのか、具体的に伝えていく必要があります。
先生のメリットを示して、お願いする

親御さんが一方的にお願いしても、むずかしいケースがあります。先生も多忙です。
余裕がなかったり、必要性を感じていないケースもあるため、お願いする場合は、必ず先生のメリットになる伝え方をします。
例えば「移動教室の前に、個別で1回声掛けをして見通しを立てて頂けると、癇癪にならず先生が対応することが減ると思います」
など、先生が協力することで、先生自身の負担が軽くなることを、具体的に伝えらえると、協力が得やすくなります。
具体的な行動でお願いする

先ほどの親御さんの関わりと、同じになります。
先生にお願いする場合も、「誰が、いつ、どこで、何をする」のか、具体的に伝えます。これは先生が、実践しやすくするためです。
熱心でスキルもある先生であれば、具体的な表現でなくても大丈夫です。ただ、そうでない場合は、流されてしまうことも多いです。
必ず、実践できているか、ポジティブな変化があるのか、確認できるようにします。
【ADHDの子の子育てに役立つ本 5選】まとめ

記事のポイントになります。
✅ADHDの子の育児 オススメな本
・ADHDの本
・魔法の言葉かけ
・ADHDの子の育て方のコツがわかる本
・ADHDのペアレントトレーニング
・ADHDの子どもたちをサポートする本
✅本がオススメな理由
・低予算で学べる
・自分のペースで学べる
・包括的に学べる
✅活用法① 1日1回、本の知識を実践する
・具体的な行動で決める
・継続できるものにする
・日常生活の中で、できることにする
・振り返る
✅活用法② 配慮を先生に依頼する
・先生のスタンスを把握する
・先生がどう感じているか、把握する
・先生のメリットを示して、お願いする
・具体的な行動でお願いする
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】








































[…] 【ADHDの子供の親向け】おすすめのADHDの本【厳選5冊】 […]
[…] 【ADHDの子供の親向け】おすすめのADHDの本【厳選5冊】 […]
[…] 【ADHDの子供の親向け】おすすめのADHDの本【厳選5冊】 […]
[…] 【ADHDの子供の親向け】おすすめのADHDの本【厳選5冊】 […]
[…] 【ADHDの子供の親向け】おすすめのADHDの本【厳選5冊】 […]
[…] 【ADHDの子供の親向け】おすすめのADHDの本【厳選5冊】 […]
[…] 【ADHDの子供の親向け】おすすめのADHDの本【厳選5冊】 […]
[…] 【ADHDの子供の親向け】おすすめのADHDの本【厳選5冊】 […]
[…] 【ADHDの子どもの親向け】おすすめのADHDの本【厳選5冊】 […]
[…] 【ADHDの子どもの親向け】おすすめのADHDの本【厳選5冊】 […]
[…] 【ADHDの子どもの親向け】おすすめのADHDの本【厳選5冊】 […]
[…] 【療育支援員がおすすめ】ADHDの子の子育てに役立つ本を紹介~厳選5冊~ […]
[…] 【療育支援員がおすすめ】ADHDの子の子育てに役立つ本を紹介~厳選5冊~ […]
[…] 【療育支援員がおすすめ】ADHDの子の子育てに役立つ本 5冊 […]
[…] 【療育支援員がおすすめ】ADHDの子の子育てに役立つ本を紹介 5冊 […]